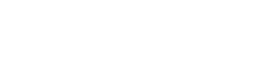イラン核施設攻撃に対する日本政府の対応に関する声明
2025.07.03
「法の秩序を守るべく、外交による解決で主導的役割を」
ピースデポ代表 鈴木達治郞
2025年7月3日
6月13日のイスラエル、さらには6月22日の米国によるイランの核施設への攻撃に対し、日本政府は「二重基準」の対応を行った。イスラエルに対しては「極めて遺憾であり今回の行動を強く非難する」との外務大臣談話を発表したが、米国の攻撃に対する談話では「(米国の対応は)イランの核兵器保有を阻止するという決意を示したものと承知しています」とむしろ、米国の行動を肯定的に述べたのである。
イスラエル・米国の軍事攻撃は、いずれもイランから武力攻撃される前の先制攻撃であった。ともに国連憲章第51条で認められている「自衛権」に当たるとは到底思われず、「(国際)法の秩序」を守ることを外交の原則としている日本政府の声明としては、極めて不適切と言わざるを得ない。さらに、核施設への攻撃は、危険な施設への攻撃を禁止している国際人道法の精神にも矛盾する。
7月3日現在、一時停戦が実現していることは歓迎すべきことではあるが、今後のイラン・米国の交渉の行方によっては再び軍事対立が起きる可能性は否定できない。イランの核能力は完全に破壊された証拠はなく、そもそも軍事力で核拡散を防止することはできない。むしろ、イランの核武装への動機を強めることになりかねない。イランが核不拡散条約(NPT)を脱退する可能性が現実のものとして危惧される事態となった。世界の核不拡散・軍縮体制にとって大きな懸念につながってしまった。
日本政府としては、まず何よりも再び軍事衝突を起こさないように、イスラエル・米国に対し「国際法の遵守」を訴えるべきだ。そのうえで、イランに対しても、国際原子力機関(IAEA)の要請に真摯に対応して『核の疑惑』を払拭し、NPTから脱退しないよう強く要請すべきだ。米国に対しても、JCPOA(共同包括行動計画)を参考に、イランの原子力平和利用の権利を認めつつ、核拡散リスクを最小にする方向で交渉を進めるよう求めるべきだ。さらに、これを機に、中東非核・大量破壊兵器地帯交渉への交渉参加や、NPT第6条の遵守など、NPT体制の堅持に必要な行動を米国に強く訴えるべきだ。
日本はイラン・イスラエル・米国と良好な外交関係をもつ重要な関係国であり、国内に多くの原子力施設や核物質を抱える国としても他人ごとではない。日本政府としては、軍事力による力の政治ではなく、「法の秩序」に基づき、外交に基づく問題解決を3か国に強く訴え、核軍縮・不拡散分野で主導的役割を果たすことを強く要請する。